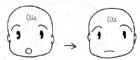離乳食のページ
問い合わせ番号:10010-0000-2758 更新日:2023年4月1日
「離乳」とは、母乳やミルクを飲んで育ってきた赤ちゃんが、固さや形を変えながら少しずつ幼児食に移行する過程を言います。乳汁を吸うことから、食物をかみつぶして飲み込むこと、食品の量や種類が増えていき、形態も変化していきます。また、食べる行動は手づかみ食べなど、次第に自立へ向かっていきます。

あまり難しく考えずに、大事なことは・・・
離乳食の内容や量は、お子さんの食欲や成長や発達を尊重して、個々に合わせて進めていくことが大切です。離乳食の目安表もありますが、量、種類はあくまでも目安です。
あまり難しく考えずに進めていきましょう。
食べる量が適量かを判断するには、子どもの身長、体重が母子健康手帳に記載されている乳児身体発育曲線(男女別)のカーブに沿っていれば大丈夫です。
食べることの楽しさや、五感(見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触る)による脳への刺激は大きく、情緒、発語、消化器官の発達など、お子さんの健やかな心身の発達には欠かせません。

スタートの月齢は5ヵ月くらいから
遅くとも生後6ヵ月には開始しないと、発達への悪影響があることがわかってきています。
未熟児で小さく生まれたお子さんのご家族は、修正月齢でお子さんにあわせてゆっくり進めてあげてください。
言葉はわかっていないからと思いがちですが、ご家族のあたたかい言葉がけや笑顔は、お子さんの食べる力を育む原動力になります。

- 離乳食の目的は、親子の信頼関係を築くことや、お子さんの摂食行動の発達を促し、食べることの自立にあります。
- お子さんの健やかな発達に大切な成長ホルモンや消化酵素等の分泌を促す、「生活リズムをつくること」が大切です。そのため幼児期に向けて、規則的な授乳や離乳食、排泄、睡眠で生活リズムをつくりあげていくことが大事になります。
- お子さんの自立の世界が広がる「歩き始める頃」までは、食後や食間の授乳(母乳、ミルク)が大切です。
- 母乳の成分は、お母さんが食べたもので作られます。より良い母乳分泌のためにも、お母さんも栄養バランスに気をつけてしっかり食べましょう。
- お子さんの発達に合わせた離乳食で、「食べる力」を育みましょう。
- 家族で食卓を囲んで、一緒に楽しく食べる体験をさせてあげましょう。
スタートするには?
- 首がすわった~縦抱きしやすくなった~
- 支えてあげると座れる~親の足の間など、支えてあげるとしばらく座っていられる~
- 食べ物に興味を示す~家族が食べていると、欲しそうに見ている&よだれがでている~
- スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる
離乳食の進め方の目安、食欲や口の動き、成長や発達に合わせて
|
月齢の目安 |
離乳の開始 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 区分 |
離乳初期 |
離乳中期 |
離乳後期 |
離乳完了期 |
|
食べ方の目安 |
お子さんの様子を見ながら、1さじから始めましょう。 母乳やミルクは飲みたいだけ与えましょう。 |
1日2回食で食事のリズムをつけていきましょう。 いろいろな味や舌ざわりを楽しめるように食品の種類を増やしていきましょう。 |
食事のリズムを大切に、1日3回食に進めていきましょう。 家族一緒に楽しい食卓経験を。 |
1日3回の食事のリズムを整えましょう。 自分で食べる楽しみを手づかみ食べから始めましょう。 |
|
食べさせ方のポイント |
姿勢は、体と首の角度に注意しましょう。 ひざに抱いた赤ちゃんの姿勢を、少しだけ後ろに傾けると、食べさせやすいです。 |
平らなスプーンを下くちびるの上にのせ、パクッと唇ではさみとるようになります。 1さじを多すぎずに。 |
やわらかめのものを前歯でかじりとらせて一口量の学習もする時期です。 | ご飯を小さなおにぎりにしたり、ゆでた野菜を手で持てる大きさに切って手づかみ食べを十分にさせましょう。 |
|
口の動き |
口に入った食べ物を、飲み込むことができる位置まで、送ることを覚えます。
|
口の前のほうを使って食べ物を取り込み、舌と上あごでつぶして飲み込む動きを覚えます。
|
舌と上あごでつぶせないものを、歯ぐきの上でつぶすことを覚えます。
|
食べこぼしながら、引き続き前歯で一口量をかじりとることを覚えていきます。
|
|
硬さの目安 |
なめらかにすりつぶした状態。 (ポタージュ状) ↓ |
舌でつぶせる固さ。 (豆腐くらい) |
歯ぐきでつぶせる固さ。 (バナナくらい)
|
歯ぐきで噛める固さ。 (肉団子くらい) |
|
食事の目安 |
「すりつぶしたおかゆ」から始めましょう。 すりつぶして、ポタージュ状にした野菜なども試してみましょう。 慣れてきたら、つぶした豆腐なども試してみましょう。 |
主食・主菜・副菜をそろえて。 お子さんの食欲や成長・発達の状況に応じて、種類や量を増やしていきましょう。 適量を判断するには、母子健康手帳にのっている乳児身体曲線のカーブに沿って伸びていれば大丈夫です。 |
||
|
味付け |
味付けなし |
|||
|
食事の回数 |
1回 | 2回 | 3回 | 食事のリズムをつけ、生活のリズムを整えていきましょう。 |
|
授乳の回数 |
食後+お子さんが欲しがるだけ。 (授乳のリズムを整えましょう) |
食後+1日3回程度 | 食後+1日2回程度 |
離乳食の進み具合に応じて与えましょう。 歩き始めをとらえて哺乳びんを卒業し、コップで飲む練習をしましょう。 |
|
手の動き |
手伸ばし行動 | 熊手型つかみ |
親指と人指し指のつまみ食べ。 手づかみ食べ。 |
手づかみ食べが上手になる・スプーン、フォークが持てる。 |
- お子さんの成長とともに、だんだん離乳食の量が増えてきます。
- 形のある食べ物をかみつぶして食べられるようになり、エネルギーや栄養素の大部分を食事からとれるようになれば離乳は完了です。
- 3食をしっかり食べられるようになったら母乳(哺乳びんのミルク)は卒業しましょう。
- 離乳の完了の頃は、お母さんに食べさせようとしたり、食事を通して親子のやりとりが楽しくなる時期です。
- 離乳が完了しても、奥歯が生えそろう3歳頃までは、食べ物の固さ、大きさ、味付け等に配慮しましょう。
さあ、離乳食を始めよう!!体調や機嫌のよい日にスタートしましょう。
|
区分 |
5~6ヵ月頃
|
7~8ヵ月頃
|
9~11ヵ月頃
|
|---|---|---|---|
|
いつ? どのくらい? |
|
|
|
|
どんなもの? |
|
|
|
|
チェックポイント |
|
|
|
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当
電話番号:0463-82-9604